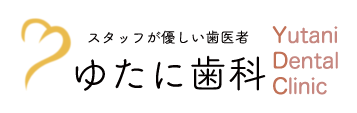咀嚼力が低下するとどのような問題があるか?
こんにちは。
西明石にある歯医者、ゆたに歯科クリニックの中島です。
普段、何気なく食事をしていますが、「しっかり噛むこと」を意識したことはありますか?
咀嚼(そしゃく)は単なる食べる動作ではなく、私たちの健康に深く関わっています。
しかし、歯を失ったり、噛み合わせが悪くなったりすると、咀嚼力が低下し、さまざまな問題が生じる可能性があります。
今回は、咀嚼力の低下がどのような影響を及ぼすのかを詳しく解説します。
1. 消化器官への負担
食べ物をよく噛まないと、大きなまま飲み込んでしまい、胃や腸に大きな負担をかけます。
唾液には消化酵素が含まれており、よく噛むことで消化がスムーズに進みます。
しかし、咀嚼が不十分だと消化不良を起こし、胃もたれや便秘、下痢などの症状が出ることがあります。
2. 栄養バランスの偏り
咀嚼力が低下すると、硬い食べ物を避けるようになります。
例えば、肉や生野菜、ナッツ類などは噛む力が必要な食品ですが、これらを避けることでタンパク質や食物繊維の摂取量が不足し、栄養バランスが崩れてしまう可能性があります。
特に高齢者では、噛めないことで食が細くなり、栄養不足から体力の低下につながることもあります。
3. 誤嚥(ごえん)のリスクが高まる
食べ物をうまく噛めないと、飲み込む動作(嚥下)がスムーズにいかなくなります。
その結果、食べ物や飲み物が誤って気管に入る「誤嚥(ごえん)」のリスクが高まり、誤嚥性肺炎を引き起こす原因にもなります。
特に高齢者では、誤嚥が命に関わることもあるため、注意が必要です。
4. 脳の活性化が低下
噛むことは、脳を刺激し活性化させる重要な役割を担っています。
咀嚼によって脳の血流が促進され、記憶力や集中力の向上に寄与します。
しかし、噛む回数が減ると脳への刺激が減少し、認知機能の低下を引き起こす可能性があります。
実際に、咀嚼力が低下した高齢者では、認知症のリスクが高まるという研究結果も報告されています。
5. 顎の筋力低下と顔のたるみ
噛む動作は顎の筋肉を鍛える重要な役割を持っています。
しかし、咀嚼回数が減ると顎の筋肉が衰え、フェイスラインがたるんだり、ほうれい線が深くなったりする原因になります。
特に若い方でも、柔らかいものばかり食べていると、顔の筋肉が衰えやすくなるため注意が必要です。
6. 歯並びや噛み合わせの乱れ
歯はバランスよく使われることで正しい位置を保っています。
しかし、噛む回数が減ると、特定の歯に負担がかかり、歯並びが乱れたり、噛み合わせが悪くなったりすることがあります。
また、歯周病や虫歯のリスクも高まるため、定期的な歯科検診が重要です。
咀嚼力を維持するための対策
咀嚼力を維持するためには、以下のような習慣を意識すると良いでしょう。
1. よく噛む習慣をつける
1口あたり30回以上噛むことを意識すると、消化を助けるだけでなく、顎の筋肉のトレーニングにもなります。
2. 硬いものや食物繊維を含む食品を取り入れる
根菜類(ごぼう、にんじんなど)や噛みごたえのある肉類を積極的に食べることで、自然と咀嚼回数が増えます。
3. 口周りの筋肉を鍛える
「あいうべ体操」などの口周りの筋肉を鍛えるトレーニングを取り入れると、噛む力の維持に役立ちます。
4. 歯の健康を保つ
歯が1本でも抜けると、噛む力が大きく低下します。虫歯や歯周病を予防し、必要に応じて適切な治療を受けることが大切です。
まとめ
咀嚼力が低下すると、消化器官への負担、栄養バランスの偏り、誤嚥のリスク、脳の活性低下、顎の筋力低下など、多くの問題が生じます。
日頃からよく噛むことを意識し、歯の健康を保つことが大切です。
もし噛みにくさを感じる場合は、お気軽に歯科医院へご相談ください。